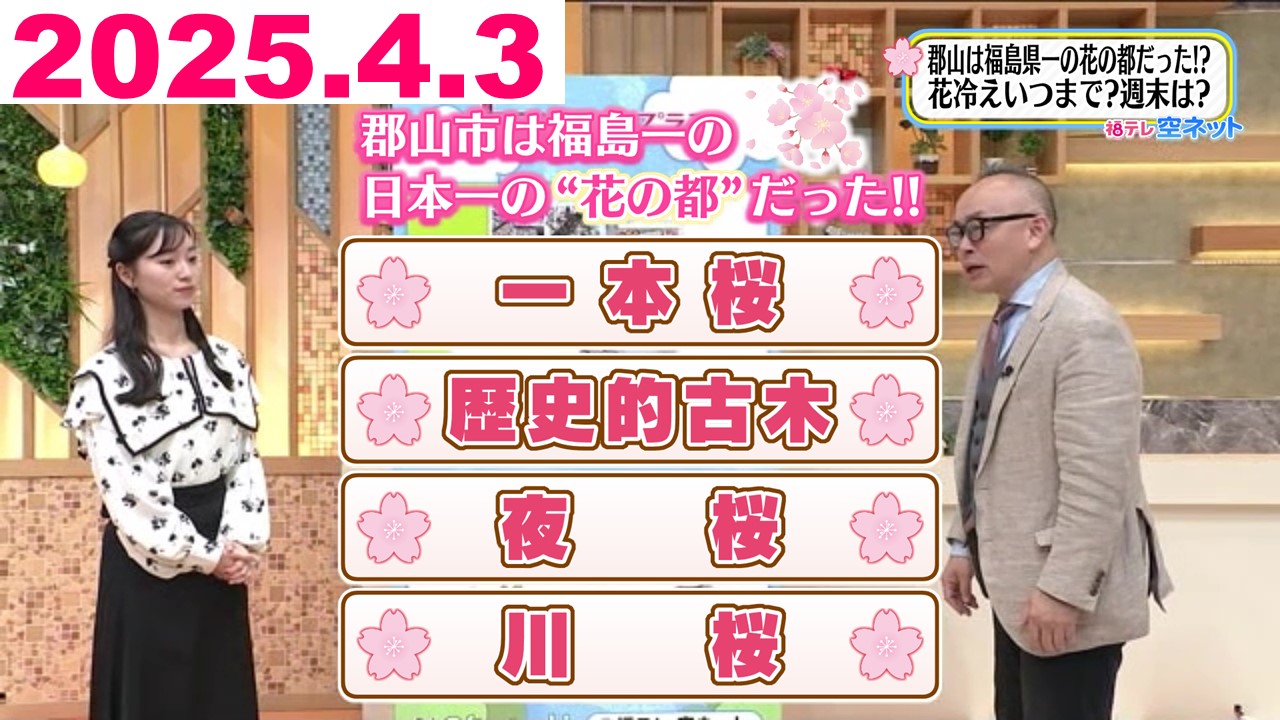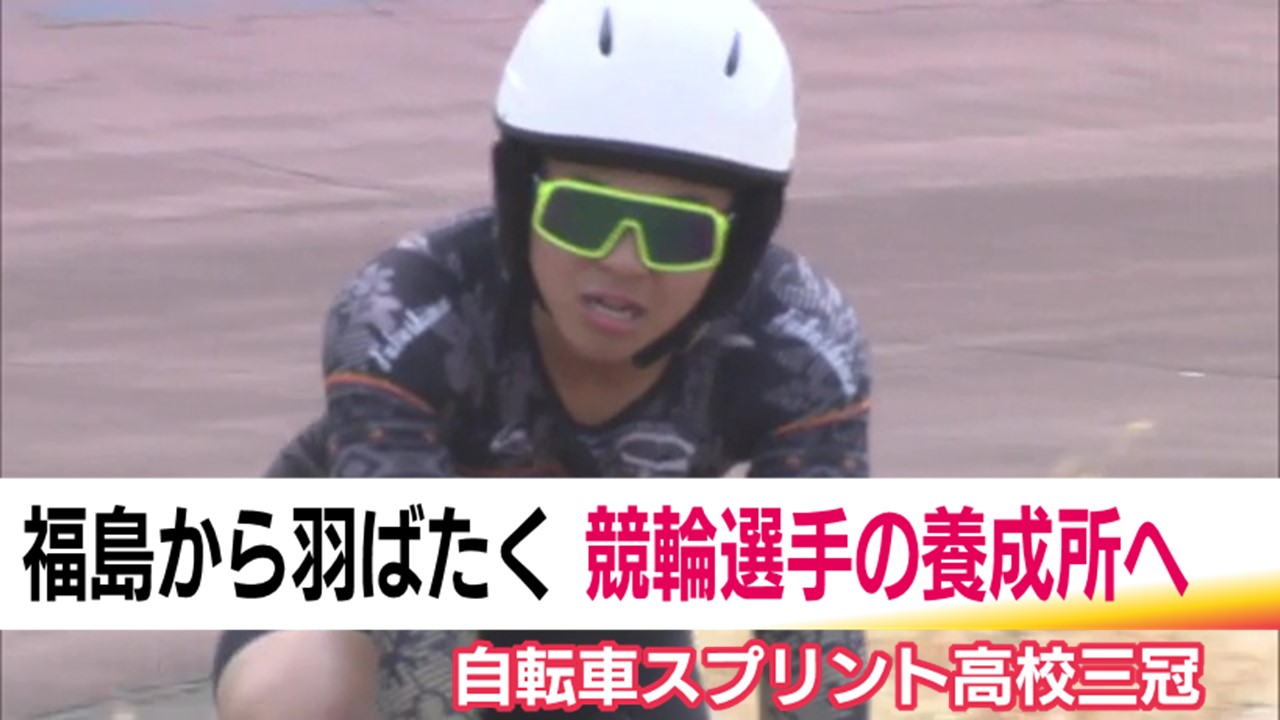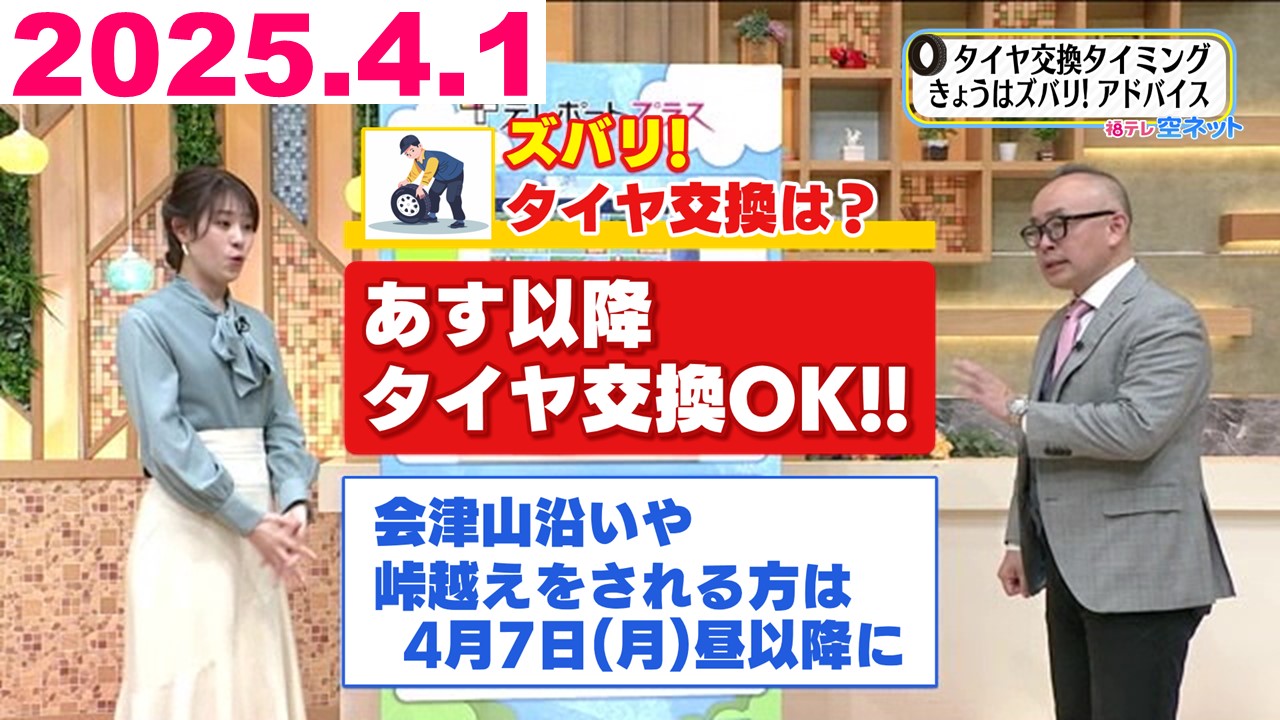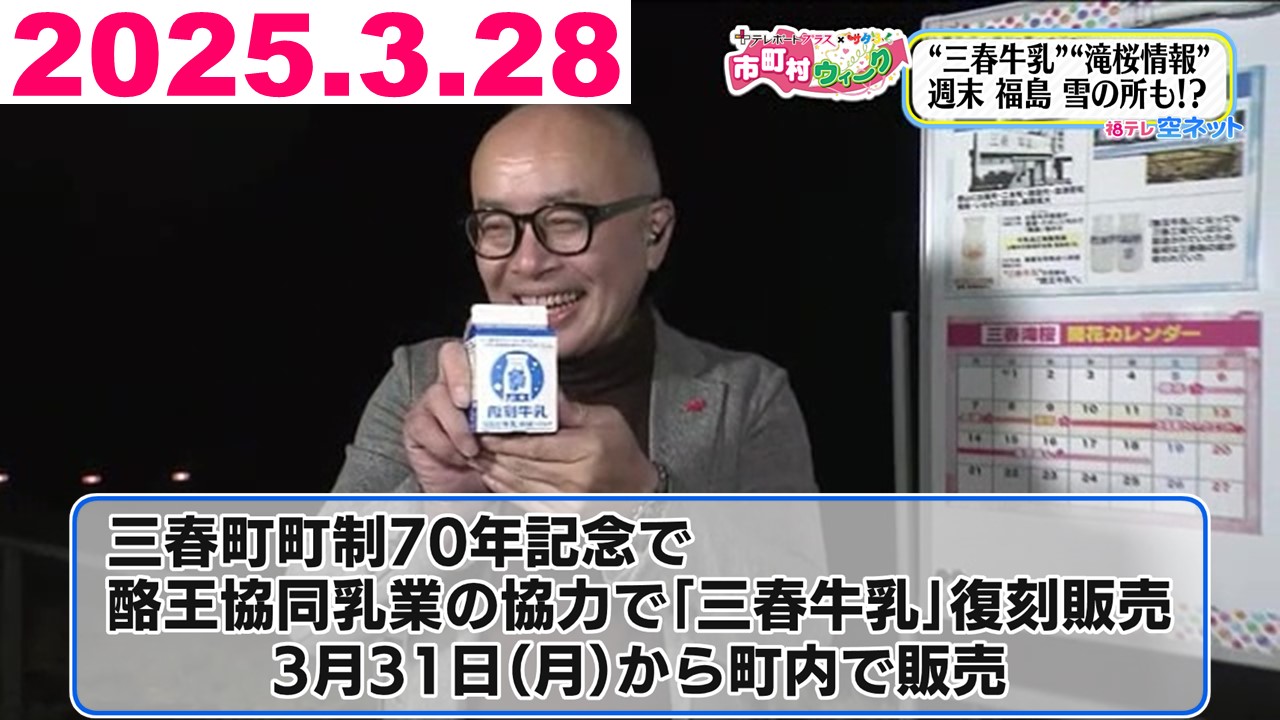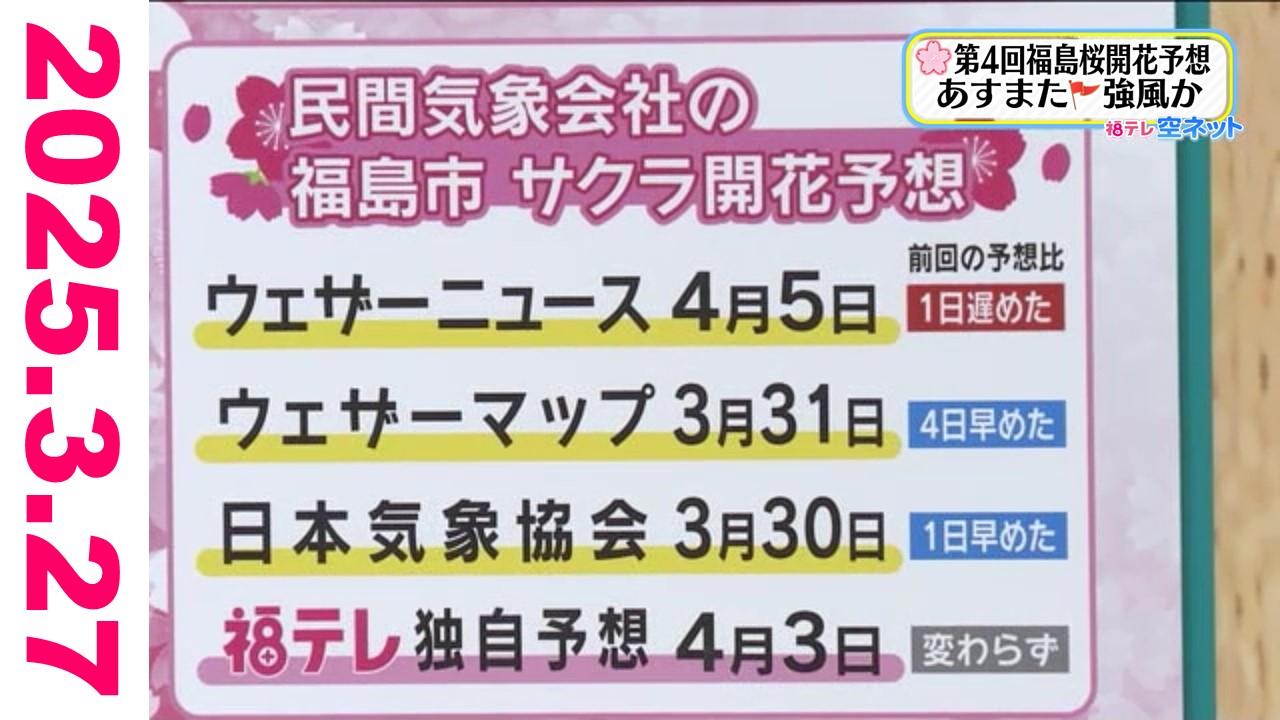テレビ番組テレポートプラス
伝統芸能の担い手不足 途絶えた江戸時代末期から続く神楽が復活

福島県内で2023年一年間に生まれた子どもは9000人あまりで、過去最少となった。
少子化がもたらすのは、経済や社会の停滞だけではない。地域をつなぎ、心のより所となる「伝統」。担い手が不足するなか、その存続をかけて一歩を踏み出す人たちがいる。
◇【動画で見る】動画はYouTube 福島ニュース【福テレ】でご覧いただけます。
途絶えた福田十二神楽の歴史
午後7時すぎ。江戸時代末期から約160年続く、福島県新地町の伝統芸能「福田十二神楽」の練習が始まった。子どもたちが紡ぎ出す笛や太鼓の音色が、町の夜を華やかにする。
神楽の指揮を務める目黒英宏さんは、小学3年生のときに福田十二神楽に出会って約50年になる。時代を超えて地域を繋いできた神楽の歴史は、5年前に一度、目黒さんの目の前で途絶えた。
少子化による担い手不足
神楽が奉納される福田諏訪神社の宮司でもある目黒さん。伝統の維持に力を尽くしてきたが、子どもたちを中心とする神楽は少子化の影響で担い手不足となり、活動の中断を余儀なくされてしまった。
目黒さんは「もともと子どもたちが少なくなったところで、震災もあってそういう雰囲気ではなくなった。時代の変化というか、うちだけではなくてどこもそうだと思うが、非常に厳しい」と話す。
地域の伝統芸能の衰退
福島県内の人口減少は東日本大震災で拍車がかかり、地域の伝統芸能にも影響を及ぼした。
震災前、浜通りに360あった民俗芸能の団体は震災直後に6割にまで減り、いまはもとの4分の1にあたる90団体にまで減った。(※「NPO法人民俗芸能を継承するふくしまの会」調べ)
授業として学ぶ...そして復活
「時代」に「伝統」が負けていいのか...目黒さんたち保存会は動き出した。
町の子どもたちがやってきたのは目黒さんの神社。福田十二神楽の舞台を「授業の一環」として見学する。目黒さんは4年前から子どもたちへの神楽の「授業」をはじめた。
「子どもたちと神楽の出会い」を教育の一環とすることを町や学校も了承し、地域の子どもたち全員が担い手候補となることで、3年前に福田十二神楽は復活を遂げた。
つながった伝統を未来へ
学年が上がっても神楽を続けたいと、熱意を持って練習に取り組む子どもたちもいる。子どもたちは「受け継いでいる人が少ないと聞いて、少しでも地域のためになれたらと思って」「授業を通して楽しさとかそういうのが分かって、そこから最終的には引き継ぎたいって思えるようになった」と話す。
目黒さんは「太鼓の音とか笛の音を聞くと、何となく体が踊りたくなるっていうかはしゃぐというか、一生忘れないのです。いつか子どもたちが、一旦ここを離れて何十年後かに帰ってきたときに、神楽がお祭りがあると、やっていたことを嬉しく思ってくれるようなところを目指して、私ができる限りやっていきたい」と話した。
いつか大人になったこの子たちが、神楽の音色を頼りにふるさとに帰れるように。
目黒さんはこれからも「未来」のための「伝統」を守り続ける。統」を守り続ける。