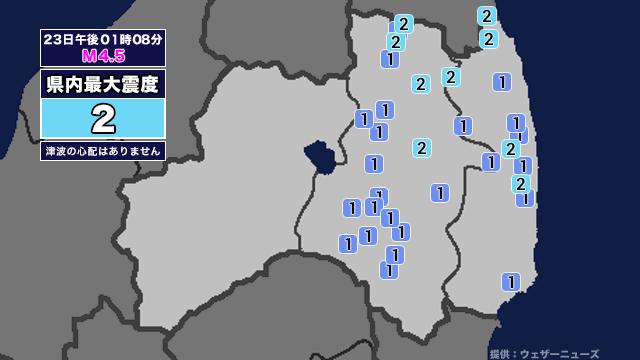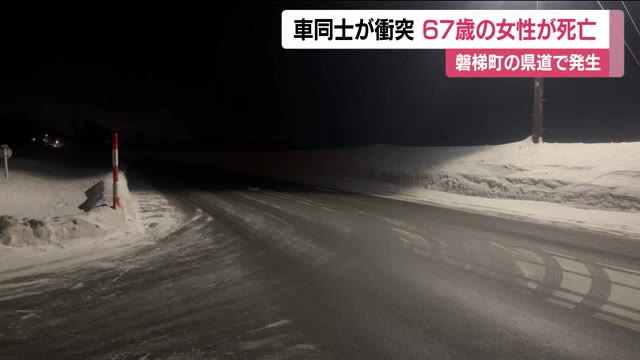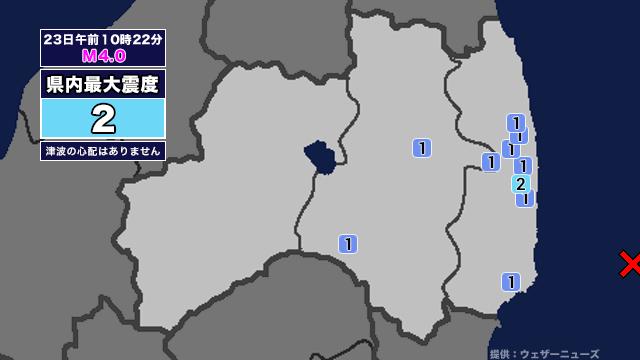身近な防災拠点と市民の防災意識《わがまち防災自慢・須賀川市編》水害の多い街で川と共に暮らす

災害から住民の命を守るために、市町村では様々な防災対策を進めている。市町村の代表者である市町村長や住民代表から、それぞれの地域の防災「わがまち防災自慢」について話を伺う。今回、東京大学大学院の客員教授で防災行動や危機管理の専門家・松尾一郎さんが訪ねたのは、福島県須賀川市。
■市民が集う防災拠点
防災マイスターの松尾一郎さんが、須賀川市の大寺正晃市長と訪れたのは市内を流れる釈迦堂川の脇に作られた「西川中央公園」。市民の憩いの場となっていて、バスケットとかジョギングも楽しめるが、実はこの地域の防災の拠点でもある。
阿武隈川の支流である釈迦堂川は2019年の東日本台風で氾濫。この台風で、須賀川市では3人の犠牲者と、1000棟を超える住宅被害が発生した。
この西川中央公園を含む地域も、最大で3.6メートルほど浸水し今後、同じ規模の災害が発生した場合、浸水面積は約1.6倍に拡大するおそれがあるという国の試算もある。
■ポンプ施設 逃げ遅れの防止へ
被害の拡大を防ごうと、2024年4月に供用開始されたこの公園には、たまった水を強制的に排水する「ポンプ施設」が整備された。大寺市長は「25メートルプールを約2分で排水することができる。これで内水氾濫の心配を、少しは軽減できたと思っている」と話す。
またポンプの能力を超える雨が降った場合でも、掘り下げられた広場には25mプール42杯分の水をためることができる。東日本台風クラスの雨でも、一杯になるまでには80分ほどかかり、逃げ遅れの防止につながることが期待されている。
■ハード面とソフト面での防災
釈迦堂川流域は古くから水害の被害も多く、2024年3月に福島県内で初めて「特定都市河川」に指定された。浸水対策の強化エリアとなったこの地区では、住民同士の訓練なども行われている。
大寺市長は「私たちは行政として、ハード面やソフト面それぞれに防災対策を進めているところ。しかし近年、日本各地で想定外の気象状況が発生していて、すべての被害を防ぐことは困難を極める中で、いかに被害を少なくできるかを考えていかなければならない。災害発生時は、行政の対応には限界がある。それを是非ご理解いただき、地域住民同士が支え合うことが人命を救う身近な方法だということを、今後も様々な機会を通じて伝えていきたい」と話した。
■市民も自主的に防災に取り組む
災害が起きやすい場所だからこそ、行政だけでなく市民側からの行動も起きている。
釈迦堂川沿いにある丸田町町内会では、2019年の東日本台風で200世帯あまりあった住宅のうち、高台を除いてほとんどが床上・床下浸水被害に遭った。
この地区に住む鈴木重さんも、自宅が浸水した一人だ。
「私も避難が遅れた。道路まで水が来たとしても、さすがに家にまでは来ないだろう大丈夫だろうなんて思っていた。避難して助かったけど、水の流れがすごかった。私の場合は、避難しなかったら死んでいた」と鈴木さんは振り返る。
■想定通りにいかない避難
これまでの経験から、避難を決断するのに時間がかかってしまったという鈴木さん。避難行動も想定通りとはいかなかった。「懐中電灯以外、何にも持たないで避難してしまった。これが不思議でならない」と話す。鈴木さんは「避難は早く、そして事前の準備、それをまず持って出るというのが一番」と語った。
■川と共に暮らす
鈴木さんは、東日本台風の被害から約2カ月後に住民たちで立ち上げた「安全で安心して暮らせる町づくりの会」の会長を務め、堤防のかさ上げや河川の整備などを行政に要望してきた。
「まだまだ対策は不安定。会で集まって、もっと町民のみんなに知っていただいて、何かあったらいち早く避難するという意識を高めていく」と話す鈴木さん。被害から5年あまりが経ったいま、行政によるハード面の整備を継続して訴えることはもちろん、「川とともに暮らす」自分たちの防災意識も変わらず持ち続けることが重要だと考えている。
防災マイスターの松尾一郎さんは「自宅の構造や自身の年齢も考慮して、どうなったら避難するというトリガーを決めておくことは大事」と話す。年々激甚化する災害に、自身の「避難のタイムライン」も定期的に見直しをかけてほしい。