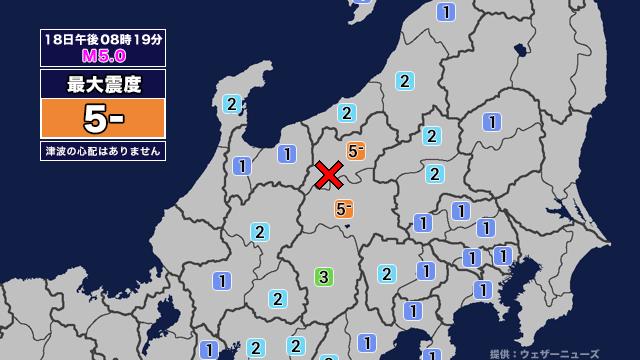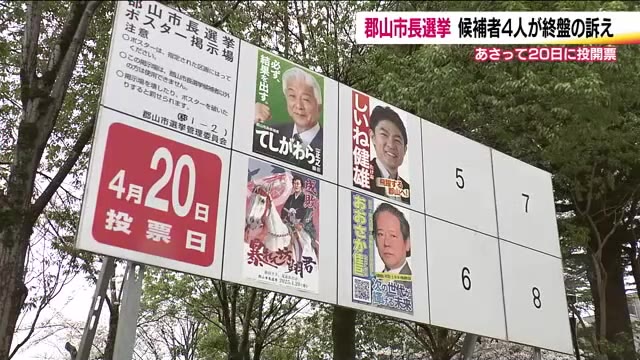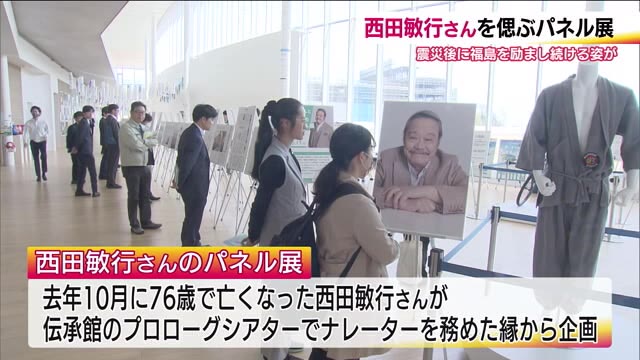<福島第一原発>つかんだ“燃料デブリ”画像公開 前回のカメラトラブルは克服

燃料デブリの試験的取り出しが行われている福島第一原子力発電所2号機で4月17日、ロボットが燃料デブリをつかみ持ち上げることに成功し、つかんだ燃料デブリの画像を公開した。
今後ロボットの引き戻し作業を行い、つかんだ燃料デブリを格納容器の外に出す計画。
燃料デブリの試験的取り出しは事故後2回目。
第一原発2号機では2024年11月、事故後初めてとなる燃料デブリの試験的取り出しに成功し、0.7gの燃料デブリが茨城県や兵庫県の研究施設で分析されている。
前回の取り出しでは、ロボットが燃料デブリを一度つかんだ後、遠隔確認のためのカメラからの映像が途絶えるトラブルが発生。作業の継続が困難として、デブリを引き上げず一度中断しカメラを交換した経緯がある。
原因は現場の高い放射線によりカメラ内部に電気がたまってしまったものと推定されていて、今回は部品を交換するとともに、カメラのON/OFFを繰り返すことが不具合につながる可能性もあることからON状態のまま作業を行っていた。
燃料デブリが順調に取り出されれば、前回と同じようにまずは茨城県の研究施設に運ばれる計画。前回と同様に“3グラム以下”の取り出しとなる見込みで、燃料デブリを格納容器の外にまで引き戻し、放射線を遮るコンテナに格納し終える“試験的取り出しの完了”は週明けになると見られている。
福島第一原発の1号機から3号機にあるデブリは880t。
国と東京電力は2051年までの廃炉完了を掲げている。
※追加情報(4月17日午後5時20分)
東京電力は燃料デブリのつかみ取りの経緯について「初めに燃料デブリを2個つかんでしまったように見えたため、しっかりつかみなおそうとして移動したところ2つに分かれた。しっかりとつかめていることを確認できたためそのまま作業を継続した」としている。
大きさはロボットのツメの大きさにおさまっているとみられ、ツメの大きさの7mm以内と見られている(去年11月に採取したものは約9mm×7mm)。
【燃料デブリ試験的取り出し・これまでの経緯】
■2021年:当初の試験的取り出し着手予定
⇒ロボットの開発遅れ、経路への堆積物の詰まり発覚などで延期
■2024年8月22日:試験的取り出し着手を計画するも「現場での棒の順番ミス」が発覚し取りやめ
⇒東京電力が現場に立ち会っていなかったことなどが問題に。
管理体制の見直しを行う。
■2024年9月10日:試験的取り出し作業に着手
■2024年9月14日:ロボットが一度デブリをつかむ
■2024年9月17日:カメラ4台のうち2台の映像が見られなくなるトラブルで中断
⇒高い放射線が影響でカメラ内部に電気がたまり不具合を起こしたと推定。
カメラ交換を決断。
■2024年10月24日:カメラの交換作業を完了
■2024年10月28日:試験的取り出し再開
■2024年10月30日:デブリの把持・吊り上げに成功
■2024年11月2日:デブリを事故後初めて格納容器外へ取り出し成功
■2024年11月5日:放射線量が「取り出し」基準クリアを確認
■2024年11月7日:試験的取り出し作業完了
■2024年11月8日:デブリの水素濃度などが輸送の基準を満たすこと確認
■2024年11月12日:事故後初めてデブリを第一原発構外へ 研究施設へ輸送
■2024年12月26日:JAEA「採取デブリからウラン検出」公表し「典型的な燃料デブリ」と評価
■2024年12月:デブリの非破壊分析が完了・分析機関に分配するためデブリを砕く
■2025年1月8日:JAEA「5つの分析機関への分配決定」公表
■2025年1月10日:デブリの一部をJAEAからMHI原子力研究開発株式会社(NDC)に輸送
■2025年1月22日:デブリの一部をSPring-8とJAEA原子力科学研究所に輸送完了
■2025年1月31日:デブリの一部をJAEAから日本核燃料開発株式会社(NFD)に輸送。予定されていたすべての研究施設への輸送が終了。
■2025年3月25日:2回目の採取に向け前回ミスがあった「棒の順番ミス」の訓練開始
■2025年4月14日:東京電力「準備が整った」として4月15日に2回目採取に着手することを公表
■2025年4月15日:ロボットの先端が格納容器につながる扉を通過し「2回目の採取着手」
■2025年4月17日:燃料デブリの2回目の把持・吊り上げに成功