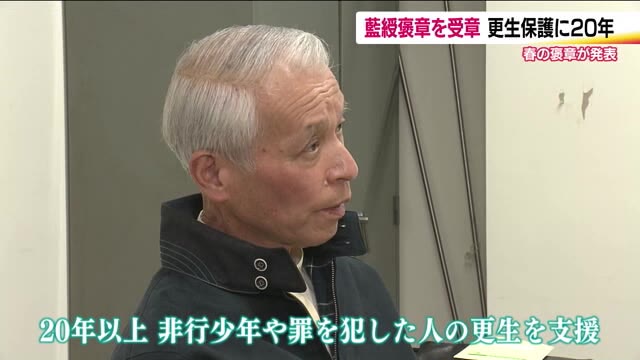<福島第一原発>2025年度初回の処理水放出が完了

東京電力は福島第一原子力発電所での処理水の海洋放出について、2025年度1回目の放出を4月28日午前11時50分に完了したと公表した。
福島第一原発では2023年8月に処理水の海洋放出が開始された。今回の放出は通算12回目で放出量は約7800t(タンク約8基分)。4月10日から実施され、トラブル等は確認されていない。
第一原発では2023年の放出開始からこれまでに合わせて約9万4000t(タンク約94基分)の処理水が薄められて海に放出された。
2024年4月には原発構内でのケーブル敷設のための掘削作業で誤って地下の電源ケーブルを傷つけるミスがあり、停電の発生によって放出が約6時間半にわたって停止するトラブルがあったが、以降、放出の停止などに関わる目立ったトラブルは発生していない。
2025年度は、7回に分けて約5万4600t(タンク約55基分)を放出する計画で、これまでに海洋モニタリングで異常などが確認されていないことなどから、放出する処理水に含まれるトリチウムの濃度を2024年度よりも高くする方針。
東京電力は第一原発周辺海域で海水のトリチウム濃度測定を実施していて、発電所から3km以内で700ベクレルを検出した場合には放出を停止することとしているが、これまでにこの指標に達したことはなく、調査実施レベル(1リットルあたり350ベクレル)にも至ったことはない。海洋放出中の4月25日に採取された海水のトリチウム濃度の最大値は沖合1.5kmで1リットルあたり23ベクレル、4月26日採取分では検出限界値未満となっている。
第一原発には、事故で溶け落ちた核燃料が金属やコンクリートなどを巻き込んで固まった「燃料デブリ」が約880tあると推計されている。地下水や雨水がこの燃料デブリに触れると「汚染水」となり、ここから大部分の放射性物質を取り除いて「処理水」の海洋放出を行っている。「燃料デブリ」は2024年11月に事故後初めて約0.7gの採取に成功、2025年4月には2回目0.2gの採取に成功した。採取されたデブリは合わせても全体の10億分の1程度。燃料デブリが存在し続ける限り汚染水は発生する。
処理水放出は、敷地を圧迫する1000基あまりのタンクを減らし、廃炉のためのスペースを開けることが大きな目的のひとつ。
2025月2月からは、放出によってカラになった溶接型タンクの解体も始まっていて、まずは12基を2025年度中に解体する見込みとなっている。空いたスペースには燃料デブリの取り出しに関する施設を建設する計画。東京電力は廃炉の進捗に伴い、必要な施設を建設するためのスペースを作る計画を立てながらタンクの解体を実施していきたいとしている。
東京電力は処理水放出に伴う海域への影響の不安の解消につなげようと、2022年9月から"通常の海水"と"海水で希釈した処理水"、さらに放出が始まってから"実際に放出された処理水"を使って、ヒラメやアワビ、海藻などの飼育試験を行ってきたが「生体内でトリチウムは濃縮されない」などの結論が得られたとして、2025年3月31日で試験を終了した。
一方、処理水放出以降、中国による日本産海産物の禁輸措置など、影響は続いている。
中国は2025年4月7日、2月にIAEA・国際原子力機関の枠組みで実施した海水や魚の分析結果を明らかにし「異常は認められない」としながらも「今後の検査でも問題がないとは保証できない」とし、モニタリングを続ける姿勢を示した。
東京電力は3月26日までに処理水放出に関して約600件・570億円の賠償支払いを完了したと公表している。1か月前と比べて約60件・20億円増加していて、ホタテやナマコを中心に、中国が日本産海産物の禁輸措置をとっていることによる取引中止の損害が多くを占める。
中国は、IAEAによる監視を拡充し、安全性が確認されれば措置を解除する方針を示しているが、現状で具体的な解除のスケジュールなどは決まっていない。
国と東京電力が掲げる廃炉の完了は2051年。
タンク内のトリチウムがゼロになるのも2051年と計画されている。