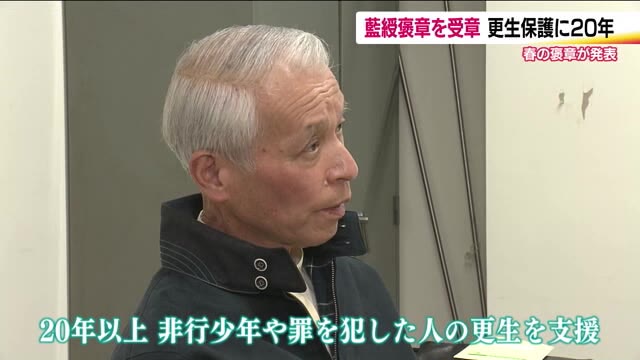"遠隔"専門人材を一極集中 20人規模の新たな組織を設置へ<福島第一原発>

東京電力は福島第一原子力発電所に、約20人規模の新組織「遠隔技術活用推進室」を立ち上げるべく、原子力規制委員会に申請を行ったと公表した。申請は2025年4月23日付。
東京電力によると、福島第一原発では、放射線量が高く作業員が近付けない場所での作業を行う際に、ドローンやロボットなどを遠隔で操作して実施しているが、各作業またはプロジェクトごとに遠隔操作の技術やノウハウが散らばった状態になってしまっているという。これを取りまとめ、専門人材を一極集中させる組織の設置を検討している。規制委員会の認可にかかる時間が見通せないため、設置時期は未定としている。
福島第一原発2号機では2025年4月23日に原発事故後2回目となる燃料デブリの試験的取り出しが完了した。事故で溶け落ちた核燃料が金属やコンクリートなどを巻き込んで固まった"燃料デブリ"は非常に強い放射線の発信源となっているため、人が近づくことはできず、ロボットを用いて遠隔操作で行われた。
また、燃料デブリの採取に至ってない1・3号機では格納容器の内部調査が進行している。
2024年2月から3月にかけては、1号機の格納容器内部で初めてとなるドローン調査が行われ、核燃料が入っている「圧力容器」の底から"つらら"のようにぶら下がっている物体や、塊状の物体といった「核燃料由来のデブリの可能性」のあるものを確認した。
3号機ではドローンを入れることができる配管の大きさが小さいため、1号機の調査で使用したドローンの3分の2ほどの大きさ、約12cm四方の「マイクロドローン」を用いて2025年以降に調査を行う計画を示している。
一方、福島第一原発には燃料デブリ以外にも強い放射線を発するものが存在する。
地下水などが燃料デブリに触れて発生した"汚染水"を浄化して"処理水"にする過程での通り道になっている建物には、事故当時から"汚染水"を浄化しようと、放射性物質を吸着するためのゼオライトの土のうが大量に投入された。
ゼオライト土のうの表面線量は1時間あたり4400ミリシーベルト(2024年11月に2号機から採取された燃料デブリの500倍超)で、時間の経過によって劣化して破れるなどして、大部分が地下に流れ込み"汚染水"に浸かってしまっている。ゼオライト土のうだけでも2つの建屋に合わせて約1300袋・26tが残されていると推計されている。
2025年3月からはじまった回収作業も、作業員の被ばくを避けるために遠隔で行われていて、2026年度から2027年度まで続く見通し。
東京電力はこのように「福島第一原発の廃炉作業は現場環境の特異性や作業員の被ばく防止の観点から、遠隔技術が不可欠」として、「今後の廃炉を着実に進めるために専門人材を一極集中させる」としている。
「遠隔技術活用推進室」は福島第一原発での遠隔作業の設計から操作までの支援を行う組織としていて、どのような作業をサポートしていくかについては検討中。
国と東京電力は2051年までの福島第一原発の廃炉完了を掲げている。