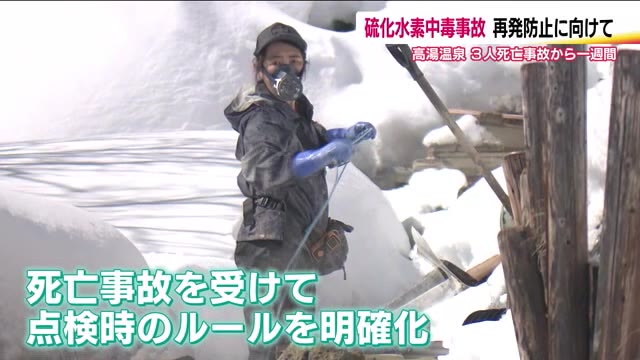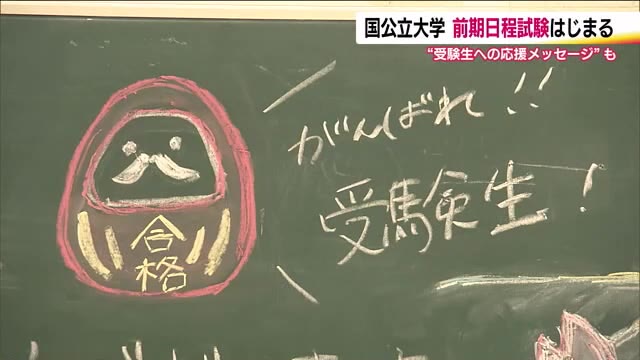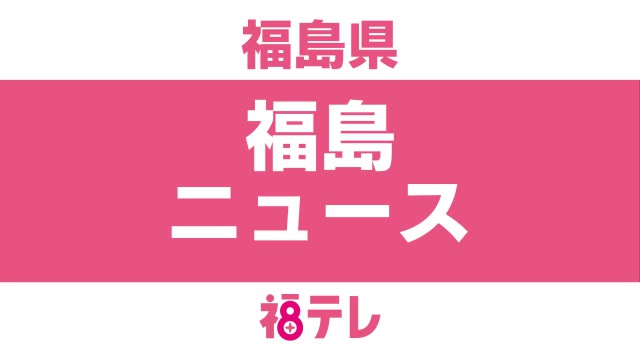環境大臣「再生利用の運搬費用は国が持つ」中間貯蔵施設への理解醸成目指す<会見詳細>

浅尾環境大臣は2月25日の会見で、中間貯蔵施設に保管されている除去土壌について、再生利用を進めるにあたり、「除去土壌や覆土をそこに運ぶ費用は当然国が持つ」とした。
双葉町と大熊町にまたがる中間貯蔵施設は、2025年1月末の時点で1406万立方メートルの除去土壌が搬入されている。
国は、全体の約4分の1にあたる「比較的放射能濃度が高いもの」については量を減らして県外最終処分、それ以外の約4分の3にあたる「濃度が比較的低いもの」は公共事業などで再生利用する計画。
再生利用をめぐっては、2月24日に双葉町の伊澤町長が「首都圏の人たちへの理解を進めるには、まずは福島県内で再生利用に取り組む必要がある」として、個人的な考えだと前置きしたうえで「町のインフラ整備で必要になったタイミングで、住民・議会の理解を得て町内での再生利用を考えていきたい」と発言していた。
一方、最終処分については、2045年3月までの福島県外での実施が法律で定められているが、具体的な場所は決まっていない。
【2月25日・浅尾環境大臣の会見】
Q 2月24日の双葉町の伊澤町長との会談について「国としてもしっかりやっていく」とはどのような意味か?
A 伊澤町長からは、県外最終処分や復興再生を含めた様々な国の取り組みがなかなか進んでいかないということに、中間貯蔵施設の立地自治体として危機感を持っているということ、全国的な理解醸成をより一層進めてほしいという考えを伺った。
私からは、理解醸成を含む県外最終処分に向けた取り組みについて責任を持って進めていくという話をさせていただいた。
Q 会談の中では、双葉町長から町内での受け入れについての話はあったのか?
A そういった話はない。
Q 双葉町長の懸念とは?
A 理解醸成が遅れていて、それに対する危機感を持っているということ。
Q 再生利用を自分の町での受け入れも含めて検討していかなければいけないという発言が、中間貯蔵施設の立地自治体から出たことをどう受け止めるか?
A 県外最終処分というのは国の約束。最終処分の構造ないし容積を決めていくにあたっても、再生利用できるものについて検討を進めていくことが大変重要で、理解の醸成を責務として行っていく。閣僚会議も設置をしているので、できるだけ双葉町長も安心できるような形で進めていきたい。
Q 再生利用を双葉町内などで進めることについて可能性があると考えるか?
A 制度面だけの話で言えば、再生利用については県外県内問わず、これは法的な問題はないと理解をしている。ただ大変量が多いので、できるだけ全国で再生利用ができるようにしてないと、最終処分の量が減らないという課題がある。
Q 仮に福島県内で再生利用が行われたとすると、県外最終処分に向けて国民の理解醸成が進んでいくと考えるか?
A あくまでも最終処分については県外でというのは法律で決まっている。これは理解の有無を超えてやらなければいけないと思う。
それに加えて再生利用については閣僚会議を設置をして進めているところだが、放射線に関する認識を高めていかなければいけない。再生利用を想定しているものについては覆土をするが、覆土をしない状況で、そこで1年間仕事をしても、放射線の量は1ミリシーベルトということで、発がん性等々全く関係がない。その上さらに覆土で厳しく、問題ない形にして再生利用をするが、そういったことの理解を進めていかないと行けない。
Q 再生利用の場所を募るにあたり、受け入れ自治体に対するインセンティブは?
A 当然、その再生利用をしていただくにあたって除去土壌、覆土をそこに運ぶ費用は当然国が持つ。その他のことについては特段決まっていることはない。
Q 費用以外にも、メリットは必要か?
A メリットというより、国民の皆さんが安全なものだと理解していただければ、その土壌を使う方がコスト的には安いのかそうでないのかという判断になる。
Q 環境省として今後決定する再生利用の基準を活用して丁寧に説明していきたいということだが、具体的な数字を進めることで理解が深まると考えているのか?
A 1キロ当たり8000ベクレル以下の除去土壌について再生利用をしていくということで考えている。8000ベクレルという数字は、1年間で1ミリシーベルトの放射線ということだが、1ミリシーベルトがどういうものなのかということは国民の皆様に理解をしていただく必要がある。
例えば発がん性との関係でいうと、100ミリシーベルトを超えると野菜不足でがんになるのと同程度の発がん性。1ミリシーベルトはがんとの関係性で言えば有意性はないということだが、そういった科学的事実を伝える必要性がある。
Q 除染土壌の最終処分に向けては、理解醸成も含めてそもそも国の責任で進めていくものであって、再生利用について中間貯蔵施設の立地自治体が発言をしなければいけない状況になったことを大臣としてはどう受け止めているか?
A 中間貯蔵施設を受け入れていただいた自治体の町長が、県外最終処分や再生利用の取り組みをもう少し理解が進まなければいけないという思いを持っていることについては、大変深く受け止めているし、国としても理解を進めていくことに繋げていかなければと思う。中間貯蔵施設を受け入れていただいた町長に対して大変申し訳ないと思う。